6G6Gと6Z-P1は特性が似ているところがある。そこで6G6Gシングルアンプに6Z-P1を挿してみることにする。
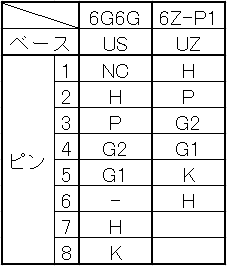
6G6GはベースがUS、6Z-P1はUZだから変換ソケットを作成する。ピンコネの表を上記に示す。

作成したUS→UZの変換ソケット。
タマころがしをして聴いてみて良い音だった!だけでは意味がないので、特性を調べておくことにする。

6G6Gを6Z-P1に変更した回路図に実測の電圧を赤字で記入した。電圧配分は6G6Gとほぼ同じ。

諸特性。NFB無しは内部の端子の配線を外す必要があって面倒なのでやらなかった。出力は0.8Wくらい。6G6Gシングルアンプの特性と比べてみても殆ど同じ。
Analog Discoveryによる周波数特性。

参考にクロストーク特性。20Hz~20kHzでは-76dB以下だった。
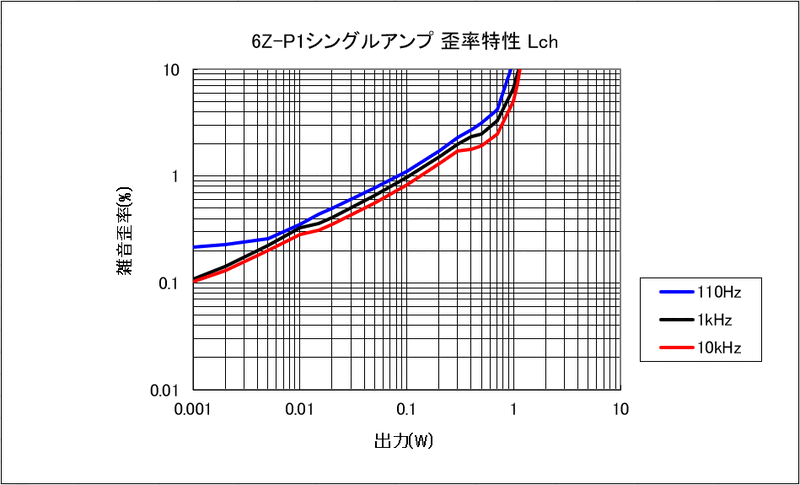
Lchの歪率特性。2次歪み主体の直線状で、0.1Wにおける歪率は1%くらい。これは6Z-P1の3結における直線性が悪いことに起因する。
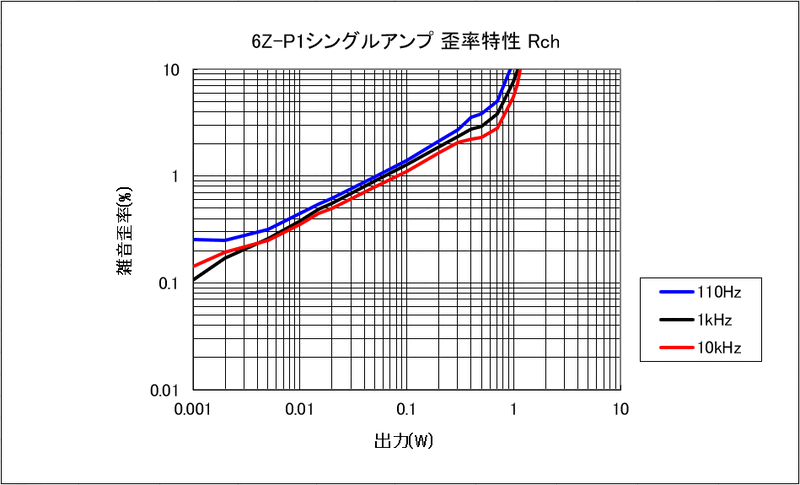
Rchの歪率特性。Lchと同様だが0.1Wにおける歪率は1.5%くらい。
3階自室で試聴。当初雄大なスケール感にビックラこいたが、利得が21倍前後あってボリュームを上げすぎたのと、信号ショートループのコンデンサとOPTの1次インダクタンスによる低域共振があるためだろう。直熱管のような透明感や音場感はあまり感じられない。聴いていて心地よいのは2次歪みによるものか。装飾のようなものはあると思うけど聴いて良いのなら許したら。好みかどうか聞かれたら、好みと答えるだろう。
出力管にP-G帰還を施したら歪率は半分程度に減少すると思う。但し高域カットオフ周波数が下がってくるけど。
6Z-P1は6G6Gをもとに日本で作られたらしい。なら日本製の6G6Gでも良かったのでは。
6Z-P1を6G6Gに戻してみた。聴き慣れた音場感、音色に艶が戻ってきた。私には6G6Gのほうが好みのようだ。6Z-P1も良い線いっていると思うけど。


